
山口県光市で1999年に母子2人が殺害された事件で殺人や強姦致死などの罪に問われた元少年の被告人(30)の死刑が確定することになった。2月20日、被告人の上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)が上告を棄却する判決を言い渡したからだ。被告人は、大月(旧姓福田)孝行。犯行時18歳1カ月だった。事件と判決が問いかけた課題を追った。
少年法は18歳未満の死刑を禁じている。また、「刑罰ではなく保護更生」を原則とし、少年事件の審理では、少年の行状、経歴、素質、環境等について、心理学や教育学などの専門的知識、少年鑑別所の鑑別結果を活用するよう努めることが要請されている。
そのため、18歳以上の少年に、更生可能性を奪う死刑を科すかどうかが注目された。何を基準にして更生と死刑との線を引けばいいのか--。
<「永山基準」を踏襲>
判決理由が弁護人の上告趣意を上告理由に当たらないと退けたうえで、あえて「付言すると」として取り上げた事情の検討は、「永山基準」と呼ばれる死刑適用基準に沿った総合判断そのものだった。
「永山基準」とは、4人を拳銃で射殺した犯行時19歳の永山則夫元死刑囚に対する判決で、最高裁が1983年に示した基準だ。(1)犯行の罪質、(2)動機、(3)態様、とくに殺害方法の執拗性・残虐性、(4)結果の重大性、とくに殺害された被害者の数、(5)遺族の被害感情、(6)社会的影響、(7)犯人の年齢、(8)前科、(9)犯行後の情状--の9項目を総合的に考慮して、「その罪責が誠に重大であって、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、死刑の選択も許される」としたもの。
一方、「厳罰化」としてクローズアップされた2006年の第1次上告審判決の「18歳になって間もないことは死刑を回避すべき決定的事情とはなり得ない」とした判断について、今回の判決は一切触れなかった。
実務経験を持つ研究者からは、「06年判決は死刑適用基準として一般化するものではないという最高裁のメッセージ」との指摘がある。(原田國男慶応大客員教授、西日本新聞2月21日付)
<少年法の要請にこたえたか>
差し戻し控訴審判決は、被告人について、母親の自殺や父親の暴力などが人格形成に影響があり、精神的成熟度が低いと認定し、量刑を検討するに当たって情状として考慮したうえで、死刑を選択した。
同じく死刑を言い渡した今回の最高裁判決は、宮川光治裁判官が反対意見を述べ、裁判官でも判断が分かれた。
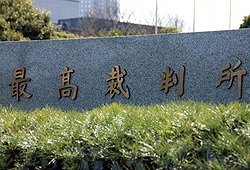 宮川裁判官は「精神的成熟度が18歳を相当程度下回っていることが証拠上認められるような場合は、死刑判断を回避するに足りるとくに酌量すべき事情が存在するとみることが相当」として、「再度、量刑事情を検討して量刑判断を行なう必要がある」と高裁に差し戻すことを求めた。少年の経歴や生育環境についての専門科学的解明という少年法の要請に基づいて、被告人の精神的成熟度について審理を尽くせば、死刑を回避すべき特段の事情にあたる可能性があるというのである。
宮川裁判官は「精神的成熟度が18歳を相当程度下回っていることが証拠上認められるような場合は、死刑判断を回避するに足りるとくに酌量すべき事情が存在するとみることが相当」として、「再度、量刑事情を検討して量刑判断を行なう必要がある」と高裁に差し戻すことを求めた。少年の経歴や生育環境についての専門科学的解明という少年法の要請に基づいて、被告人の精神的成熟度について審理を尽くせば、死刑を回避すべき特段の事情にあたる可能性があるというのである。
また、少年保護の理念に基づいて死刑を科してはならないとする国連決議(1985年「少年司法運営に関する国連最低基準規則」)の尊重をあげて、18歳以上の少年には死刑をできる限り回避する方向で適用すべき、との考えも示した。
<「新供述」を否定>
一方、金築誠志裁判官は反対意見に対する補足意見で、差し戻し後の控訴審が人格形成上の問題や精神的成熟度について審理を怠っていないし、なおざりにしていないとしている。
反対意見は、少年法の精神を尊重し、被告人が犯した罪と正しく向き合う可能性をみたが、それには、「適切な処遇」と「時間」が必要とした。
ただし、反対意見も「(差し戻し控訴審での)被告人の供述態度を誠に残念」と述べ、「母胎回帰ストーリー」という動機が存在するという鑑定意見は採用できないと明確に否定したことを忘れてはならない。
死刑と更生のはざまで、具体的にどこで線を引くのか。答えが明らかになったというよりも、結論を出す難しさを浮き彫りにした判決だった。
※記事へのご意見はこちら
